ハノイとホーチミンの人種が違う——ベトナム開発で“土地の個性”を武器にする実践ガイド
- Daisuke Neigisi
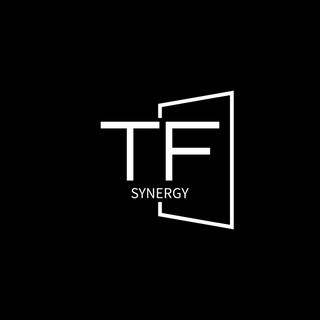
- 2025年11月12日
- 読了時間: 7分
まず最初に:本タイトルの「人種」は比喩表現です。差別的意図は一切なく、**ハノイ(北部)とホーチミン(南部)それぞれの“ビジネス文化・働き方の個性”**を示すために使っています。本記事では、その違いを理解し、プロジェクト成功確率を上げるための体制設計・コミュニケーション設計までを具体的に解説します。
誰のための記事か
これからベトナムオフショア開発を始めたいが、やり方がわからない企業
すでに始めたが炎上・停滞している企業
新規事業を立ち上げたいが、要件整理~開発~運用までの推進方法が不明な企業
企画から運用監視まで一気通貫で任せたいが、何から手をつけるべきか迷っている企業
まずは相談先を一本化したい企業
TomorrowFuture株式会社(TF)は日越デュアルショアで、上流(企画・要件)から運用監視までの一気通貫を支援しています。本記事は実戦的な設計図としてお使いください。
概観:ハノイとホーチミンの“性格差”を一言で
ハノイ(北部):堅実/設計重視/規律と合意形成を尊ぶ/品質・手戻り抑制に強み
ホーチミン(南部):スピード/市場志向/プロアクティブ/試作・仮説検証に強み
成功のコツは“どちらが良いか”ではなく、「自社プロジェクトのフェーズと性質」に最適化して使い分けること。
典型的な強み・弱み(現場感に基づく仮説)
観点 | ハノイ(北部) | ホーチミン(南部) |
得意領域 | 大規模案件、官公庁・金融系に近い厳密性、設計/レビュー工程 | スタートアップ的開発、PoC/プロトタイプ、UI改善の素早い反復 |
マネジメント相性 | ウォーターフォール寄りの工程管理、成果物ベースの合意 | アジャイル/スクラム、変更受容性、顧客開発 |
コミュニケーション | 合意に時間をかけるが齟齬が少ない | 初速が速いが前提が変わると軌道修正の対話が要 |
リスク | 仕様確定が曖昧なままだと停滞 | 要件定義が浅いと品質ばらつきや技術負債化 |
適するフェーズ | 要件定義~基本設計~結合試験 | アイデア検証~UI改善~グロース施策 |
※地域差は“傾向”であり、チームごとの差も大きい点は必ず留意してください。
失敗パターンは「地の利のミスマッチ」から起きる
要件が曖昧なのに、詳細設計・見積りを急ぐ
→ ハノイ側は精緻化を求め、時間がかかる/南部側は走り出すが後で手戻り。
“早く作る”前提で南部に任せ、品質基準が曖昧
→ デリバリーは早いが、受入時に品質議論が発生し、結局遅延・コスト増。
日本側の意思決定がボトルネック
→ 日次の小さな合意が溜まり、週次で大きな齟齬に。ブリッジSEの決裁範囲が狭すぎるのも典型。
アジャイル用語だけ導入して“儀式化”
→ スプリントレビューが単なる進捗会に。価値検証(KPI/KGI)に紐づいていない。
“勝ち筋”テンプレ:フェーズ別の都市・体制の当てはめ
フェーズA:0→1(仮説検証・スピード命)
推奨:ホーチミン主導+日本側PdM/デザイナー密着
体制:PM(日本)– PdM/UX(日本)– Dev(HCMC)– QA(Hanoi or HCMC)
鍵:KPI定義 → 2週スプリント → 隔週ユーザーテスト → データで意思決定
フェーズB:1→10(機能拡張・品質担保)
推奨:ハノイで設計・レビュー強化+南部で機能追加の平行稼働
体制:アーキ/レビュー(Hanoi)– 開発(HCMC)– QA(Hanoi)– SRE(Hanoi)
鍵:**非機能要件(性能・監視・可用性)**の明文化、変更管理のルール化
フェーズC:運用定着(SRE/監視/コスト最適化)
推奨:ハノイ中心でSRE/監視運用、南部はグロース小隊
体制:SRE(Hanoi)– Ops(Hanoi)– Growth Squad(HCMC)
鍵:SLO/SLI、オンコール、コストモニタリング(FinOps)、障害事後レビュー
ブリッジSE/PMの設計が「すべて」を左右する
悪い設計:通訳係に留まり決裁権なし/課題と原因を分離できない/スプリントで価値を語れない
良い設計:
語学+開発実務の両輪(設計/レビューを“自分で”できる)
決裁権限(ストーリーポイント/受入基準/軽微な仕様変更の即時判断)
リスクを見える化(バーンダウン、欠陥密度、MTTR、テックデット残高)
TFのデュアルショアでは、日本側PM/BAが意思決定を握り、ハノイ(品質・SRE)×ホーチミン(開発速度)を一枚絵で統制します。
契約と見積り:炎上を呼ぶ“地雷”と回避策
地雷1:成果物定義が曖昧
回避:WBSと受入基準(DoD)を契約添付。UI/UXはワイヤー/プロトタイプも合意文書に。
地雷2:アジャイルなのに固定スコープ前提
回避:時間・材料(T&M)+明確なベロシティで管理。スプリント毎に優先度をリシャッフル。
地雷3:テスト責任の所在が不明確
回避:品質責任分界(ベンダーQA範囲/発注側受入範囲)と障害SLAを明確化。
地雷4:為替・人月単価の変動吸収なし
回避:為替トリガー条項と単価改定条件を事前合意。国内・越側のミックス比率を調整可能に。
実務チェックリスト:着手前にこれだけは決める
[ ] ビジョン→KGI→KPI→主要ユースケース(1枚で説明できるか)
[ ] 優先度付きバックログ(MoSCoW)と受入基準(DoD)
[ ] 都市配分:ハノイ=設計/QA/SRE、HCMC=実装/PoC/UI改善(※プロダクト特性に応じて変更)
[ ] ブリッジSEの決裁範囲(ストーリー変更閾値、工数±%許容)
[ ] スプリントカレンダーと定例(デイリー/レビュー/レトロ)
[ ] メトリクス:リードタイム、欠陥密度、リリース頻度、MTTR、ベロシティ
[ ] 監視設計:SLO/SLI、オンコール体制、障害報告テンプレ
[ ] 契約条項:成果物/受入/変更管理/為替/単価/知財/守秘
[ ] 退避計画:ロールバック、DR、バックアップ、鍵管理
[ ] 移管計画:ドキュメント標準、コード規約、ナレッジベース
ケース:よくある“詰まり”とTFの解き方
ケース1:要件が定まらず、見積りがブレる
症状:見積りがスライドし続ける/誰も決めきれない
処方箋:2週間のディスカバリースプリントでKPI仮説→プロト→ユーザーテスト→再見積り。
体制:PdM(日本)× UX(日本)× Dev(HCMC)× 実装レビュー(Hanoi)
ケース2:受入でバグが多く、信頼が落ちる
症状:E2Eテストで落ちる/UIのズレ
処方箋:ハノイQA主導のテスト設計(テスト観点表、境界値、データ条件)+CIでの静的解析。
体制:QA/テスト設計(Hanoi)× 実装(HCMC)× 受入(日本)
ケース3:運用で障害対応が後手
症状:復旧が遅い/原因分析が属人化
処方箋:SRE(Hanoi)でSLI/SLO定義→アラートノイズ削減→**事後レビュー(5 Whys)**標準化
技術スタックと共通ルール(例)
共通:Gitフロー、PRテンプレ、Lint/Format、コードオーナー、ADR(Architectural Decision Record)
品質:静的解析(言語別)、単体/結合/契約テスト、自動E2Eは主要顧客導線のみから開始
運用:監視(メトリクス/ログ/トレース)、デプロイ戦略(Blue/Green or Canary)、Feature Flag
ドキュメント:C4モデル(System/Container/Component)、Notion/Confluenceで検索可能性担保
言語:設計・課題は日本語-英語併記(誤読を減らす)
予算感とスケジュールの考え方(目安)
ディスカバリー(2~4週間):PdM/UX/Tech Lead少数精鋭。**仮説の切り出しと“作らない決断”**が目的。
MVP開発(6~12週間):南部中心で実装、北部がレビュー・QA。価値検証を伴走。
運用定着(継続):SRE/監視・改善サイクル+グロース小隊。KPI改善に投資を集中。
同じコストでも、都市の使い分け次第で“時間価値”が大きく変わるのがベトナム開発の妙味です。
まずはここから:最小構成の“お試し”プラン(例)
2週間ディスカバリー
成果:KPI、ユーザー要件、スコープ境界、UIワイヤー、概算見積り
4週間MVPスプリント×1(HCMC主導、Hanoiレビュー)
成果:動くプロト、受入基準に基づくレビュー、次スプリントの優先度
運用・モニタリング導入(Hanoi)
成果:監視ダッシュボード、SLO、アラート運用、障害時の役割分担
ここまでで“走りながら学ぶ”体験を、低リスク・短サイクルで提供します。
まとめ:土地の個性を“戦略アセット”に
ハノイの強み=設計・品質・運用
ホーチミンの強み=速度・仮説検証・UI改善
日本側が司令塔となり、適材適所で編成することで、QCDの同時達成に近づけます。
無料相談のご案内(Note読者限定)
現在の課題の棚卸し(30分)
都市配分と体制のラフ設計
最初の2~4週間で“何をやらないか”を決めるセッション
「まずは相談」からで大丈夫です。
企画・要件定義・システム開発・運用監視まで、一気通貫でTomorrowFuture株式会社が伴走します。




コメント