ベトナム開発で成果が出る企業と失敗する企業の決定的な違い
- Daisuke Neigisi
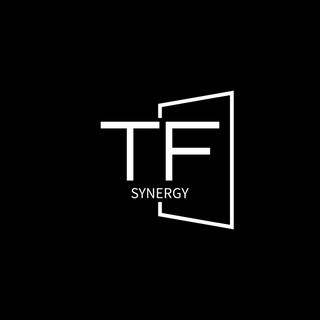
- 10月29日
- 読了時間: 8分
結論:ベトナムオフショアで成果を最大化している企業は、🎶上流~中核アーキテクチャを「日本側のシニア」*🎶握り、
実装~テストのボリュームゾーンを「ベトナム側の優秀なミドル~ジュニア」に最適配分しています。 同じ「シニア単価」を払うなら、日本人シニア×ベトナム実装チームの方が、品質・スピード・合意形成・運用安定性のすべてで総コスパが高い――これが現場で見てきた 勝ち筋です。
要約
失敗の共通点は「海外側シニアに 戦略と設計の主導権を丸投げ」し、合意形成・仕様の粒度・品質基準が曖昧なまま開発を走らせること。
成功の共通点は「日本側のシニア(PdM/アーキテクト/PMO/QA責任者)がビジョン・非機能要件・設計規範を明確化し、ベトナム側のミドル~ジュニアが反復開発でスループットを上げる役割分担」。
コスパの肝は時給ではなくTCO(総所有コスト):手戻り、リリース遅延、運用障害のリスクを日本側シニアが先回りで潰すほど、総コストは下がる。
いますぐやること:「日本側にシニア中核」「Definition of Ready/Doneの確立」「自動テスト&監視の標準装備」「日越バイリンガルPMOで意思決定を可視化」。
なぜ「日本人シニア」がコスパを押し上げるのか
1) ビジネス合意と設計判断の 時差ロスをゼロにする
要件の解釈・仕様の確定・変更判断は、日本の事業責任者やステークホルダーとの高速対話が欠かせません。ここを日本側シニアが受け持つと、
認識齟齬の火消しが 分単位で完了
日本の商習慣・法規・運用制約を前提に合意テンプレート化できる
仕様決定の遅れ=開発の空転を防ぎ、実働コストとカレンダー遅延を同時に削減
2) 非機能要件とアーキテクチャの 最初の一手が品質を決める
スケーラビリティ、可用性、セキュリティ、保守性などの非機能要件は、初期設計の数手先で決まります。日本の現場文脈に明るい日本人アーキテクトが、
技術選定の妥当性(クラウド/マネージド/自前)
モジュール境界とAPI契約
テスト戦略(E2E/Contract/負荷/セキュリティ)
運用監視(SLO/SLA/SLI、アラートしきい値)
を🎶 日本の業務要件基準🎶落とし込むほど、後戻りコストが激減します。
3) 仕様粒度の基準化で 作り直しを消す
Definition of Ready/Done(DoR/DoD)、UI/UXの受入基準、例外系の網羅など、要求の粒度を日本側シニアが🎶 誰が読んでも同じ解釈に整えます。これがあるだけで、ベトナム側のミドル~ジュニアが自走*🎶、スループットが一気に上がる。
4) リスクの早期検知と 運用を見据えた実装
日本側シニアがQA/監視/セキュリティ要件を先に設計へ埋め込み、障害を 起こさないプロダクトへ導きます。運用・監視を内蔵した設計は、🎶人件費より高い 障害コスト🎶抑えます。
失敗する企業の典型パターン
丸投げ:要件曖昧のまま「まず作って」→作り直しの連鎖。
海外側シニア依存:仕様・合意形成も海外側に任せ、日本での稟議/合意が都度詰まる。
非機能が空白:性能・監視・権限設計が薄く、リリース後の運用で爆発。
テストは 最後に:E2E・契約テスト・負荷試験が後回しで、納期直前に崩壊。
PMO不在:意思決定のログが残らず、争点が毎週蒸し返される。
人月レート至上主義:見かけの単価だけを下げ、手戻りと遅延でTCOが悪化。
成功する企業の勝ちパターン
日本側のシニア中核(PdM/アーキ/PMO/QA Lead)を先に固める
DoR/DoD、受入基準、例外ケースを標準化
自動テスト(ユニット/契約/E2E/負荷)と監視(SLI/SLO)を最初から
日越バイリンガルPMOで、議事・意思決定・リスクを見える化
短サイクルの反復(2週間スプリント)で小さく作り、早く学ぶ
開発~運用を一気通貫:設計段階で運用の席を用意
コスパ比較(イメージ試算:同規模機能を3か月で実装)
実プロジェクトに近い構成を想定した概算です。単価は市場レンジの一例。目的は🎶 単価ではなくTCO🎶いう視点を示すことです。
モデルA:海外側シニア主導 / 日本側は受け手中心
役割 | 配置 | 月数×人数 | 月額(例) | 小計 |
海外シニアTL/アーキ | VN | 3×1 | 120万円 | 360万円 |
海外SE/開発 | VN | 3×4 | 70万円 | 840万円 |
海外QA | VN | 3×1 | 60万円 | 180万円 |
日本側BrSE/窓口 | JP | 3×0.5 | 130万円 | 195万円 |
計(開発のみ) | 1,575万円 |
隠れコスト(よく発生)
仕様の再確認・作り直し:+10~20%
リリース遅延・追加検証:+5~10%
運用トラブル初期消火:+5%
→ TCO想定:1,575万 × 1.2~1.35 ≒ 1,890~2,126万円
モデルB:日本人シニア主導 / ベトナム実装チームで加速
役割 | 配置 | 月数×人数 | 月額(例) | 小計 |
日本人アーキ/TechLead | JP | 3×1 | 180万円 | 540万円 |
日本人PMO/QA Lead | JP | 3×0.5 | 150万円 | 225万円 |
日越BrSE(兼通訳PMO) | JP/VN | 3×0.5 | 120万円 | 180万円 |
ベトナム開発(ミドル中心) | VN | 3×4 | 65万円 | 780万円 |
ベトナムQA | VN | 3×1 | 55万円 | 165万円 |
計(開発のみ) | 1,890万円 |
リスク低減(よく効く)
手戻り抑制・決定高速化:▲10~15%
自動テスト/監視前提で運用事故減:▲5~8%
スプリント内受入で 後ろ崩れ減:▲5%
→ TCO想定:1,890万 × 0.8~0.85 ≒ 1,512~1,607万円
ポイント:見かけ上はモデルBの 月額合計が高く見える局面もありますが、手戻り/遅延/障害の総コストを引くと逆転します。🎶 単価ではなく 総コスト(TCO)とリードタイム*🎶評価することが、本当のコスパです。
推奨の役割分担(テンプレ)
日本側
PdM/ビジネス責任者:KPI/スコープ/優先度の意思決定
アーキテクト/Tech Lead(日本人シニア):非機能/設計規範/レビューゲート
PMO/QA Lead:DoR/DoD、テスト戦略、受入判定、変更管理
BrSE/バイリンガルPM:合意形成の潤滑油、議事と意思決定ログの整流化
ベトナム側
Dev Lead(ミドル):日次推進、レビュー、ベロシティ管理
開発(ミドル~ジュニア):設計規範に沿った実装
QA/自動化:契約テスト/E2E/負荷テストをパイプライン化
いますぐ着手すべき5つの打ち手
合意アセットの標準化
要求→仕様→受入のテンプレ・観点表・例外ケース一覧
DoR/DoDの導入
「開発に入ってよい要件の条件」「 完了の定義」を明文化
自動テストと監視の 先出し
PR時の必須チェック、SLI/SLOを設計段階で決める
2週間スプリント+スプリント受入
小さく作って小さく検収。手戻りを早期に吸収
日越バイリンガルPMO
決定・論点・リスクの見える化、合意速度を倍に
よくある反論と回答
Q:海外にも優秀なシニアはいるのでは?
A:もちろんいます。本稿の主張は国籍の是非ではなく、 合意形成と非機能要件を日本の事業文脈で最短に決める役割を日本側シニアが握ると総コスパが高いという運用設計の話です。海外シニアはDev Leadや専門領域のスペシャリストとして機能させると、全体の効率が最も上がります。
Q:日本側シニアは単価が高く、総額が増えませんか?
A:月次の見かけは増えても、TCOは下がるのが現場実感です。手戻り・遅延・障害コストを含む全体最適で評価しましょう。
Q:小規模案件でも有効?
A:むしろ小規模こそ 最初の数手が成果を決めます。要件粒度・設計規範・受入基準を日本側シニアが1~2名で先出しするだけで、費用対効果が跳ね上がることが多いです。
ケースで見る 決定的な違い
失敗例:要件定義が薄いまま一括発注 → 画面はできたが業務が回らない → 運用で付け焼き刃 → コスト増
成功例:日本側シニアが非機能と受入基準を先に固め、ベトナム側で反復実装 → スプリントごとにKPI/UXで受入 → リリース後も障害が少なく運用費が安定
新規事業・一気通貫依頼の進め方(30日ロードマップ例)
Day 0–7:Discovery/合意形成
目的・KGI/KPI、スコープ、ユーザーストーリー、制約条件を合意
DoR/DoD雛形、非機能要件(SLO/セキュリティ/監査)を草案化
Day 8–14:設計基盤の固定
アーキ選定、モジュール境界、API契約、テスト戦略、監視設計
UXモックと受入観点表
Day 15–30:反復実装×2スプリント
ベトナム側で実装、CI/CDに自動テストと静的解析を組込み
スプリント受入で 動く価値+学びを積み上げる
まとめ:勝てるチーム編成は「日本人シニア × ベトナム実装」
仕様と非機能の 解像度を上げる日本側シニアの価値は、手戻り・遅延・障害という見えづらい損失を劇的に減らします。
単価ではなくTCO。この視点で比較すれば、日本人シニアを中核に置く方が総コスパが高い。
日越ハイブリッド体制で、スピード×品質×コストを同時に最大化しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. まず相談だけでも可能ですか?
A. もちろんです。要件が固まっていない段階でも、上流の整理から伴走します。
Q. 運用監視まで任せられますか?
A. 設計段階から監視・運用を内蔵します(SLO/アラート設計、自動復旧方針、セキュリティ運用)。
Q. 途中からの引き継ぎも対応可能?
A. 可能です。現状診断→火種特定→安定化プラン→反復改善、の順で再起動します。
お問い合わせ(Call to Action)
「日本人シニア × ベトナム実装」で最短ルートを設計します。
上流の壁打ち/既存案件の健康診断/費用対効果の見直し まで、お気軽にご相談ください。
Tomorrow Future株式会社(TF)|代表:根岸大輔
お仕事のご相談はNoteプロフィールのリンク、またはX/DMからどうぞ。
Tomorrow Future株式会社(TF)
担当:代表取締役 根岸 大輔
電話:070-2021-7382(平日10:00–18:00 JST)
X(旧Twitter)DM:




コメント